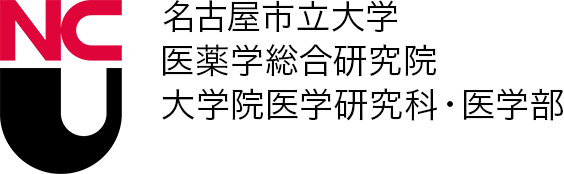2025年 第3期「脳のふしぎ × こころの健康」
最新医学講座 オープンカレッジ 2025年 第3期のご案内
- [開講日時] 令和7年10月31日(金)~令和7年12月19日(金) 毎週金曜日18:30~20:00
- [応募受付期間] 令和7年9月16日(火)~令和7年10月3日(金)
- [選考結果] 令和7年10月15日(水)
- [コーディネーター]名古屋市立大学大学院医学研究科 認知機能病態学寄附講座 教授 野村 洋
脳は精巧な機械のようでいて、感情や思いやりなど、温かなこころも生み出す不思議な臓器です。記憶や睡眠、感覚など、私たちの豊かな日常は脳の緻密なはたらきによって支えられています。一方、脳の調子が崩れると、発達障害や心の病気、慢性の痛みなど、さまざまな問題が起こります。この講座では、脳とこころの健康の深いつながりをテーマに、リハビリやケアなど身近な例を交えながらわかりやすく解説します。脳を知って、こころも体も健やかな毎日を送るヒントを見つけてみませんか。
2024年度第3期にご好評いただいた「脳とこころのサイエンス」とは異なる内容で、初めての方もリピーターの方も楽しんで学べる講座となっています。
2024年度第3期にご好評いただいた「脳とこころのサイエンス」とは異なる内容で、初めての方もリピーターの方も楽しんで学べる講座となっています。
●第1回10月31日 (金)
記憶を思い出す、思い出せない脳のしくみ
名古屋市立大学大学院医学研究科 認知機能病態学寄附講座 野村 洋
「昨日の晩ごはんは何を食べたかな?」そんな日常の疑問から、昔の懐かしい記憶まで、私たちの脳は、実に巧妙なしくみで記憶を管理しています。この講座では、記憶を”思い出す”ために脳がどのように働くのか、そして”思い出せない”のはなぜか、最新の脳神経科学の知見を交えてわかりやすく紹介します。つらい記憶は思い出さないほうが心の健康に良いこともあります。そんな”忘れることの意味”も考えながら、記憶の不思議に迫ります。
●第2回11月7日 (金)
てんかん・自閉症の分子遺伝学
名古屋市立大学大学院医学研究科 神経発達症遺伝学 山川 和弘
30億の塩基からなるヒトゲノムDNAは個人間で0.1%強の違い(300万~1000万箇所)があり、これらの違いが病気やそのなり易さなどを大きく規定しています。自閉症などの神経発達症やてんかんにおいてもこれら遺伝的背景の寄与が大きいことは一卵性双生児研究や多くの遺伝学的解析でも明らかです。また、健常な父母の重症患児の原因遺伝子新生変異(患児のみに現れる変異)のほとんどが実は父母の性腺モザイクに由来し、次子でのリスクは一般集団の数百倍となります。動物モデル研究は疾患発症メカニズムを明らかにし、治療法開発につながっています。
●第3回 11月14日 (金)
脳の可塑性とニューロリハビリテーション
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター リハビリテーション科 青山 公紀
20 世紀までは,脳をはじめとする中枢神経は再生しない、変化しないと言われてきました。しかし近年脳には失われた脳機能でも適切なリハビリテーションにより神経回路が再構築され、機能の回復を図ることができることが分かってきました。これは「脳の可塑性」と呼ばれますが、こうした脳の仕組みに着目して機能回復をはかるリハビリテーションを「ニューロリハビリテーション」と言います。この講義ではニューロリハビリテーションを中心に、脳機能に関するリハビリテーションについて解説していきます。
●第4回11月21日 (金)
うつを予防して健康に生きよう
名古屋市立大学大学院看護学研究科 精神保健看護学 香月 富士日
だれでも気分の良いときと沈んでいるときがありますが、自分の気分や感情と上手に付き合うことがうつ病予防には大切です。また高齢になると不眠の悩みが増えてきますが、不眠とうつも関係しています。今回は、うつ病予防や不眠症改善のお薬以外の方法をお伝えする予定です。
●第5回 11月28日 (金)
眠っている時の脳の話
名古屋市立大学大学院薬学研究科 神経薬理学 粂 和彦
私たちは毎晩眠りますが、必要があって遅くまで起きていることもあります。そんな時、「眠い自分」と「眠らないよう頑張る自分」が戦いますね。でも、いったい誰と誰が戦っているのですか?頑張る自分が負けると、意志に反して眠ってしまいますが、負けたのに寝てしまうと気持ち良いですね。心の機能の中でも、特に「自己」を考える時、睡眠中の脳はとても参考になります。最新科学が明らかにした睡眠中の脳を紹介しながら、心の仕組みの問題を考えます。
●第6回12月5日 (金)
脳の病気と実臨床〜ここまで進んだ病態理解と最新治療〜
名古屋市立大学大学院医学研究科 脳神経内科 間所 佑太
脳神経内科では、脳、脊髄、末梢神経、筋肉など、多岐に渡る領域の病気を診療します。このうち、脳の病気では、①アルツハイマー病、②パーキンソン病、③脳梗塞、④頭痛の患者さんが多く、その研究、治療は日々進歩しています。この講座では、これらの病気の最新のトピックスを、最前線で働く臨床医の視点からわかりやすく解説します。
●第7回 12月12日 (金)
脳神経が引き起こす痛み?慢性痛の意外な原因とは
名古屋市立大学大学院医学研究科 麻酔科学・集中治療医学 杉浦 健之
慢性痛のメカニズムは、脳や神経の誤作動が引き起こす痛みが原因かもしれません。痛みの原因が身体の問題ではない場合に、脳が痛みをどのように感じ取っているか、慢性の痛みと脳・神経の関わりについて説明します。さらに、どのようなアプローチで慢性痛診療を行っているか、当院いたみセンターの臨床現場をご紹介いたします。
●第8回 12月19日 (金)
温度や痛みを感じるしくみ
名古屋市立大学なごや先端研究開発センター 温度生物学研究室 富永 真琴
私たちは、どのようにして温度や痛み刺激を感じているのでしょうか?2021年にノーベル生理学医学賞が授与された温度感受性TRPチャネルが、感覚神経、皮膚などで温度刺激を感知して、その情報が脳に伝えられて温感や痛みが生じることが明らかになっています。辛みは味覚ではなく、痛みです。トウガラシの辛み成分カプサイシンは感覚神経でその受容体TRPV1を活性化しますが、43度以上という痛みを引き起こす熱刺激でも活性化します。そのメカニズムを分かりやすく紹介するとともに、体験もしていただこうと考えています。