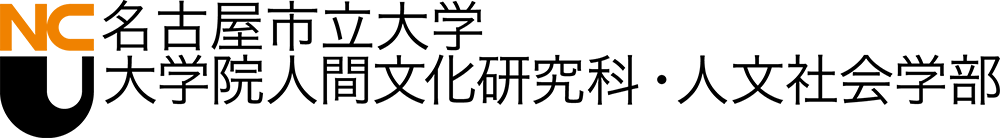人文社会学部ESDの取り組みに関するFD研修(2025年度前期)の報告
前期に実施したFD(Faculty Development:教員研修)では、新任教員の研修もかねて、ESD入門での学びの共有とともに、基礎科目で大切にしていることを確認する機会をもちました。
日 時:(1)2025年4月8日(火)午後4時半から5時まで
(2)2025年7月22日(火)午後3時から4時半まで
場 所:(1)1号館1階会議室
(2)1号館4階420教室
参加者:(1)人文社会学部教員43名(参加率93.5%)
(2)人文社会学部教員27名(参加率58.7%)
目 的:(1)ESD基礎科目を理解する
(2)新任教員を対象とした教育・研究・社会貢献・学務で思っている困りごとを共有し、解消にむけた意見交換を行う
内 容:
(1)16:30-16:40 ESD基礎科目の目的と枠組みの概説(曽我)
16:40-17:00 顔合わせ(ESD基礎科目6科目ごと)
(2)15:00-15:20 話題提供(石川)
15:20-16:15 困りごとの共有ワークショップ(三浦)
16:20-16:30 全体講評(久保田)
昨年度同様、前期FD第1回では、今年度の入学生のSDGs/ESDの学修状況およびESD基礎科目とは何かを改めて確認するための時間を持ちました。昨今の入学生は、小学校からSDGsを扱って問題解決型の学習をしてきた経験があります。SDGsが何かは既習済みで、なかにはそうした学習活動に積極的に関わってきた学生もいます。SDGsに対する考えや思いが今後、二極化していくことが予想されます。一方で、本学部が教育の軸としているESDについて知っている学生はほとんどいません。
こうした学生たちの状況を共有したうえで、ESD基礎科目で大事にしてほしいことを説明しました。当該科目6科目では、「諸問題/課題の現状を知り、持続可能な社会づくりに求められる考え方や価値観、知識、技法などを学べるようにすること」および「問題解決のプロセスに関わり、自信や希望の持てる場となるようにすること」をねらいにしています。1年生が、大学での学びは受験目的の勉強とは異なる学びであること、とくにESD基礎科目では専門科目と社会との橋渡し的な役割を担っているため、社会のなかにある「問題」とは何かを考え、自らの考え方やあり様をふり返ることが目的とされている授業であることを教員間で共有します。そのうえで、各科目に分かれて、新メンバーとの顔合わせを行い、どのような授業をしているのかを共有しました。
7/22(火)に開催しました第2回FDでは、ここ数年に赴任された新任の教員を主対象として、教育や研究、学務などにおける困り事を共有する機会を持ちました。はじめに、赴任した当初どういうことがあって、それにどう対応したのかをFD担当の石川先生から共有していただきました。つぎに、グループ間で各教員の困り事を共有し、どうしたらよいのかを先輩教員やそれを専門とする教員がアドバイスをしたり意見交換したりしました。参加者は3グループに分かれ、学科を越えたメンバー内で交流を楽しみました。最後に、研究科長からこうした場を通して、学科を越えた交流となり、親睦が深まってよかったと言葉がありました。
日 時:(1)2025年4月8日(火)午後4時半から5時まで
(2)2025年7月22日(火)午後3時から4時半まで
場 所:(1)1号館1階会議室
(2)1号館4階420教室
参加者:(1)人文社会学部教員43名(参加率93.5%)
(2)人文社会学部教員27名(参加率58.7%)
目 的:(1)ESD基礎科目を理解する
(2)新任教員を対象とした教育・研究・社会貢献・学務で思っている困りごとを共有し、解消にむけた意見交換を行う
内 容:
(1)16:30-16:40 ESD基礎科目の目的と枠組みの概説(曽我)
16:40-17:00 顔合わせ(ESD基礎科目6科目ごと)
(2)15:00-15:20 話題提供(石川)
15:20-16:15 困りごとの共有ワークショップ(三浦)
16:20-16:30 全体講評(久保田)
昨年度同様、前期FD第1回では、今年度の入学生のSDGs/ESDの学修状況およびESD基礎科目とは何かを改めて確認するための時間を持ちました。昨今の入学生は、小学校からSDGsを扱って問題解決型の学習をしてきた経験があります。SDGsが何かは既習済みで、なかにはそうした学習活動に積極的に関わってきた学生もいます。SDGsに対する考えや思いが今後、二極化していくことが予想されます。一方で、本学部が教育の軸としているESDについて知っている学生はほとんどいません。
こうした学生たちの状況を共有したうえで、ESD基礎科目で大事にしてほしいことを説明しました。当該科目6科目では、「諸問題/課題の現状を知り、持続可能な社会づくりに求められる考え方や価値観、知識、技法などを学べるようにすること」および「問題解決のプロセスに関わり、自信や希望の持てる場となるようにすること」をねらいにしています。1年生が、大学での学びは受験目的の勉強とは異なる学びであること、とくにESD基礎科目では専門科目と社会との橋渡し的な役割を担っているため、社会のなかにある「問題」とは何かを考え、自らの考え方やあり様をふり返ることが目的とされている授業であることを教員間で共有します。そのうえで、各科目に分かれて、新メンバーとの顔合わせを行い、どのような授業をしているのかを共有しました。
7/22(火)に開催しました第2回FDでは、ここ数年に赴任された新任の教員を主対象として、教育や研究、学務などにおける困り事を共有する機会を持ちました。はじめに、赴任した当初どういうことがあって、それにどう対応したのかをFD担当の石川先生から共有していただきました。つぎに、グループ間で各教員の困り事を共有し、どうしたらよいのかを先輩教員やそれを専門とする教員がアドバイスをしたり意見交換したりしました。参加者は3グループに分かれ、学科を越えたメンバー内で交流を楽しみました。最後に、研究科長からこうした場を通して、学科を越えた交流となり、親睦が深まってよかったと言葉がありました。