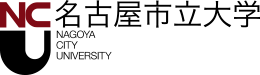人文社会学部FD研修(2024年度後期)の報告
| 活動の概要 | 後期に実施したFD(Faculty Development:教員研修)では、新学習指導要領にもとづく高校での教育活動について、高大接続を目的に名古屋市立高等学校に派遣されていた吉田先生からお話を伺う機会をもちました。また、2026年度以降に始まる新カリキュラムのもとでESD基礎科目をどのように展開していくのかを意見交換しました。 日 時:2025年3月4日(火曜日)15時から16時30分まで 場 所:滝子キャンパス1号館1階会議室 参加者:人文社会学部教員26名(参加率66.7%) 目 的:高校の教育活動を理解し、ESD基礎科目の在り方を考える 内 容: 15時から16時 講演「2022年度高校新カリと高大接続」吉田一彦先生 16時から16時30分 2026年度以降のESD基礎科目の実施方法についてのワークショップ 研修の前半部分では、吉田一彦先生(名古屋市立大学名誉教授)に「2022年度高校新カリと高大接続」という題目で、2022年度の学習指導要領の改訂に伴う高校教育と大学入試の変化について、全国の動向と名古屋市の事例を交えてお話しいただきました。 高校の新カリキュラムではいくつかの新しい科目が設けられましたが、特に多くの大学が注目するのは「総合的な探究の時間」(以下「探究」)です。吉田先生は、本学の高大連携事業の一環として、名古屋市立高校で「探究」の指導に携わってこられました。「探究」の内容は地域や学校によって差があるものの、生徒が自ら研究課題を設定し、先行研究の検討や独自の調査をおこない、その成果を論文やプレゼンテーションで公表するなど、大学での学びと重なるような実践も増えているそうです。さらに、このような高校教育の変化に呼応するように、全国の大学では総合型選抜を中心に、レポートやプレゼンテーション、ディベートなどを重視した、特色のある入試方法が台頭しているとのことです。 講演のあとの質疑応答では、高校生たちの研究水準や具体的な進路について、情報交換をおこないました。今回の講演は、「探究」を経て大学に入学する1年生に対してどのような初年次教育を提供するのか、今後の高大接続やアドミッション・ポリシー、入試についてどのような展望を描いていくのかを考える貴重な機会となりました。 研修の後半部分では、2026年度以降のESD基礎科目の在り方を考えるため、各科目で実施している手法についての情報共有を行いました。 |
| 活動の時期 | 2025年3月 |
| 担当教員 | 人間文化研究科 石川優 准教授、曽我幸代 准教授 |

吉田名誉教授の講演

ESD基礎科目ワークショップ