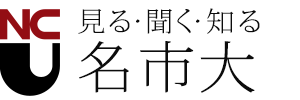卒業生の声
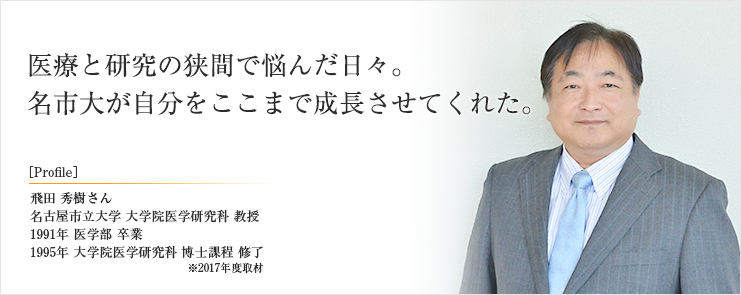
あえて研究の道に挑戦
医学部を卒業後、大学院に進んで基礎研究に従事。アメリカにポスドク(博士研究員)として留学して世界的に有名な雑誌に論文を発表し、帰国後は母校で教鞭をとり、43歳で教授となる。名古屋市立大学大学院医学研究科教授・飛田秀樹さんの経歴を俯瞰すれば、誰もが順風満帆な研究者のストーリーを思い描くに違いない。しかし飛田さん自身は、笑ってそれを否定する。

「私のキャリアは苦悩の連続でした。でも、その折々に多くの人の助言や手助けがあったから、今の私がここにいるんです」と。
名市大医学部に入学した飛田さんは「より根本的な医療に携わりたい」と思い、当時、まだiPS細胞やES細胞などという言葉を誰も知らなかった頃から細胞移植の研究に取り組んできた、日本における神経細胞移植の第一人者である西野仁雄先生の研究室に入った。
「西野研究室では、かなり自由に研究をさせてもらいました。先生は細かい指示を出す人ではなかったため、私たちは自分で考えて実験を行い、その結果から新たな課題を見つけ、多くの論文を読みまくり、次の実験を行うしかありません。でも楽しい日々でした」
医学部では、6年次に「臨床へ進み普通のお医者さんになる」か「研究をしてみたいか」という一つの選択を迫られる。要するに目の前の患者を治療する医師を目指すか、病気そのものをなくす研究者を目指すか、という選択肢だ。当然ながら名市大では多くの学生が臨床に進む。彼の周囲でも多くの友人が臨床を選んで早々に準備を始めたが、彼だけはどちらを選ぶか決めかねていた。

そんな彼を見て、同じ研究室の端谷毅先輩(当時助手)が彼に助言した。「若いうちは研究に専念して科学的なベースを身に付けた方がいい。その後、自分に研究者の才能がないと気づいたら、そこから臨床医になっても遅くない」
なるほど。確かに、みんなが臨床を選ぶなら、一人くらい違う道を行くヤツがいても面白い。こうして周囲の心配をよそに彼は臨床ではなく、研究の道に挑戦することを選んだ。しかし、医学の最先端分野は決して甘くない。どれだけ実験を繰り返しても、彼が考えるような研究成果は容易く出なかった。
「大志を抱いて頑張っても、簡単に成果は出ない。同年代の研究者が次々と立派な雑誌に論文発表するのを見て、毎日とても焦っていました」
ここでやめたら、負け犬だ
大学院で4年、研究員を含め合計で約4年半を研究に費やした。その間に結婚もした。そして大学院の博士課程も修了に近づくと、彼は再び大きな選択を迫られることになる。選択肢はもちろん、今後も研究を続けるか、臨床医として落ち着くか、の二択だ。
悩んだ彼が思い出したのは、大学院1年目に臨床実習でお世話になった、名市大医学部の先輩でもある角岡秀彦先生(元豊川市民病院院長)の言葉だった。親子ほど歳が離れた飛田さんに、角岡先生はこう告げた。
「基礎研究をすると決めたのなら、西野先生のもとでとことん研究しなさい。その上で、どうしても臨床医になりたいのなら、ウチに来ればいい」
大先輩にそこまで言われたことを思うと、逆に飛田さんの反骨精神に火がついた。また当時、温かく、かつとても熱い西野先生から言われた「戦意なき者は去れ」という言葉にも後押しされ、彼は大学院修了後も研究を続けていこうと決意した。

「もしここで研究を断念してしまったら、私はただの負け犬ですからね」
彼は西野研究室に残り、先生のアドバイスに従ってアメリカの大学・研究機関に向けて自分を売り込む手紙を送り続けた。
「言い換えれば、それは私の研究が世界的にどの程度評価されるかを客観的に知る機会でもありました」
十数通の手紙を出したところで、アメリカのシカゴ大学から「あなたを採用したい」という返事が届いた。そして彼は30歳で、シカゴ大学のポスドクとしてアメリカ留学を果たした。
「でも環境が変わったからといって、名市大で行ってきた研究の進め方が異なっているわけではありません。論文を読みあさり、考察し、実験を行い、分析する。大学院時代と同じ作業の繰り返しでした」
しかしある日、研究室のボスである教授から言われた『You have a talent.』(あなたには才能がある)という一言が彼を変えた。この場合の才能とは、自分の頭で考え、試行錯誤しながら真理に近づく力、という意味だ。しかし研究者にとっては、何よりも大切な「才能」であることは間違いない。西野研究室で過ごした日々が決して無駄ではないと分かった時、彼の苦しかった経験が大きな自信へと変わった。それ以来、後に奥さんが「毎晩、あなたは楽しそうに研究の話をしていた」と振り返るほど、彼は研究に没頭した。やがて留学前に目標としていた「世界的な科学雑誌」にも、2編の論文を発表するまでになった。 そして留学2年目、彼のところに一通の手紙が届いた。差出人は名市大の西野教授。そこには、名市大に戻って再び私の研究室で研究を続けないか、という意味の言葉がしたためられていた。
「私は西野先生にとって初めての院生でしたから、ずっと私のことを気にかけていてくださったんだと思います」
教育者になろうと腹をくくる

そして彼は名市大に戻り、西野研究室で助手として研究を続けることになった。
「実は日本に戻ってからも、あいかわらず研究者として進むべきか、それとも研究をやめて臨床医になるか迷っていました」
そして35歳の時、彼は名市大で講師に昇進し、このまま教鞭をとると決めた。それは同時に、臨床医の選択肢を自ら放棄することでもあった。
「今から思うと『研究がダメなら臨床』という考えは、自分の甘さだったと思います。講師になると決めた時、これからは基礎医学を追求すると同時に、教育者として学生の指導に人生を捧げようと腹をくくりました」
その後は幹細胞を用いた細胞移植による障害機能の再建、発育期の情動形成メカニズムなどを中心に脳神経生理学の研究を幅広く自由に行い、同時に学生の育成に力を注いできた。その傍ら、自分をここまで導いてくれた名市大に恩返しがしたいという思いから「瑞友会」(名市大医学部の同窓会)の役員も引き受けた。大学に残ると決めてからの目標だった「教授」にもなった。
常に自分自身を客観的に見つめ、研究者としての道と臨床医としての道の狭間で迷いながら紆余曲折してきた飛田さん。彼が「自らのキャリアは決して順風満帆ではない」と語る理由がここにある。
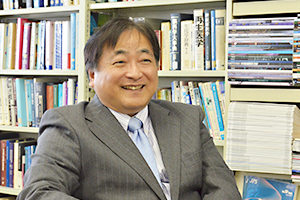
そんな飛田先生、西野研究室のDNAを受け継ぐだけあって、学生に対する思いも温かく、かつきわめて熱い。自分の都合の良いように言い逃れをする学生は、容赦なく大声で怒鳴りつけるという。
「だって、医師をめざす学生が都合よく何かをごまかすなんて、絶対にあってはならないことだと思いませんか?」
さらに、自らを育ててくれた名市大に対する思いも人一倍強い。「本学の医学部は、絶妙のポジションだと思います。先生と学生の距離が近く、先生が全員で学生を一生懸命育てる、トップに追いつけ追い越せという意識がとても強い。自由で、温かくて、本当に良い環境だと思います」
これからの目標は、自身の脳神経生理学の研究を通して、部下や学生を育てると同時に、名市大のプレゼンス(存在感)をさらに向上させること。今後も彼は、基礎研究という大海原で、順風満帆とは呼べない航行を続けていくに違いない。
プロフィール
飛田 秀樹(ひだ ひでき)さん
名古屋市立大学 大学院医学研究科 教授
[略歴]
1991年 名古屋市立大学 医学部 卒業
1995年 名古屋市立大学 大学院医学研究科 博士課程 修了
中学生の頃、テレビで救命救急シリーズを見て医者に憧れたという飛田先生。高校では周囲の反対を押し切り野球に打ち込み、現役合格に失敗。しかし浪人時代に「人間の能力に大きな個体差はないのだから、自分を客観的に見て、不足した部分を補えば人は成長する」と気づき、成績の良い知人と自分の違いを比較して知人の勉強方法を真似したところ、めきめき学力がアップしたという経験を持つ。その後、研究者になってからの方が、自分を客観視する大切さを痛感しているという。